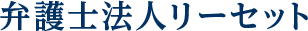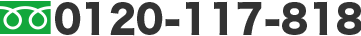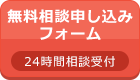包括遺贈・特定遺贈とは?|遺言書で法定相続人以外に相続させる

遺言書で第三者に遺産を贈与する際は、「包括遺贈」と「特定遺贈」のいずれかの方法を採ります。包括遺贈では渡す財産の割合を指定し、特定遺贈では渡す財産内容を指定するのですが、どちらの手段を採るかにより受遺者のメリットやデメリットが変わってきます。
ここでは、包括遺贈と特定遺贈の特徴と、遺言書で法定相続人以外に相続させる方法について解説します。
遺言書で遺贈すれば相続権を持たない第三者にも相続させることができる
故人の遺産は基本的に相続人の間で分割しますが、民法第964条によると、遺言者は自由に相手を選び、遺言書で遺贈の意思を表明することにより、相続権を持たない第三者にも財産を渡すことが可能となります。
この時、遺言者から遺贈の指定を受けた人物のことを受遺者と呼びます。受遺者が遺贈された財産を受け取るかどうかは当人の判断に委ねられます。また、相続権を持たない者が財産を相続することになるため、受遺者には相続税が通常の2割増で加算されることに注意しなければなりません。
遺贈する財産の割合を指定する「包括遺贈」の特徴
財産割合を指定して遺贈する方法を「包括遺贈」と呼びます。民法第990条では、包括遺贈の受遺者は相続人と等しく権利と義務を持つことになるため、どの財産について遺贈を受けることができるのか話し合うために、他の相続人との遺産分割協議に参加する必要が出てきます。
遺言書を作成してから相続の開始までの間に、遺産内容は変化する可能性がありますが、包括遺贈では割合だけを指定するため、変化後の遺産内容をもとに指定分を受け取ることができる柔軟性があります。また、不動産の遺贈を受けた場合、不動産取得税の納税を免れるメリットがあります。
一方、包括遺贈で受け継ぐ財産には債務も含まれるため、プラスの財産に隠れて債務が存在しないか確認する必要があります。また、他の相続人と同様、相続放棄する場合は3カ月の猶予内に手続きを済ませなければならず、その手続きはやや煩雑なものとなります。
遺贈する財産の内容を指定する「特定遺贈」の特徴
土地や現金等、故人が所有する財産から指定された分を受け継ぐのが「特定遺贈」の特徴です。何を遺贈されるのかが明確であるため、遺産分割協議に参加して調整する必要がありません。
放棄する場合期限は設けられておらず、さらに包括遺贈とは異なり債務は受け継がなくても良いことになっている点は大きなメリットであると言えます。なお、相続人が受遺者として財産を受け継ぐ場合は、特定遺贈であっても不動産取得税の納税を免れます。
一方、特定遺贈による財産分割が原因で他の相続人の遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を受ける対象となります。また、包括遺贈とは異なり、遺言書作成から相続の開始までの間に財産内容が変化していたとしても、指定された財産しか受け継ぐことができません。
包括遺贈と特定遺贈のいずれを選択すべきか
財産内容や指定方法により包括遺贈と特定遺贈のいずれかを使い分けることが大切で、その際に目安となる事柄は以下の通りです。
包括遺贈を選択した方が良いケース
自分の財産を具体的に把握していない
遺言書作成時点から相続開始時点までの間に財産内容が変化する可能性がある
他の相続人と協議しながら円満に財産分割を行って欲しい
上記のような場合では、割合だけを指定しておく包括遺贈を選択した方が、相続開始以降の遺贈がスムーズに進むことが考えられます。
特定遺贈を選択した方が良いケース
債務を負わせたくない
どの財産を遺贈するか明確にしておきたい
相続開始後に受遺者が遺産分割協議に参加せずに済むようにしたい
上記のような場合では、誰に何を渡すか明確な指定ができる特定遺贈の選択が適切であると考えられます。
遺贈により財産を受け継いだ場合も相続税を支払う義務がある
遺贈により財産を受け継いだ受遺者には相続税が課税され、その税額は法定相続人の相続税額に2割加算されたものとなります。相続権を持たない第三者が受遺者となり財産を受け取れる分、他の相続人よりも厳しい条件が付けられていることになるのです。
基本的な相続税額計算式では「(3000万円+600万円)×法定相続人数」で算出された基礎控除額がありますが、受遺者が第三者である限り法定相続人の頭数には入らないため、遺贈があった場合でも控除額が増えることはありません。
包括遺贈と特定遺贈の特徴やメリット・デメリットについて解説しましたが、遺言書作成において遺贈を検討している場合は、それぞれの方法の特徴をよく理解した上で選択することが大切です。
法的な制限や相続税額の計算にも影響してくることですので、相続の開始後に揉め事とならないよう、当事務所では早めのご相談をおすすめしています。早くご相談に来て頂ければ、その分余裕を持って様々なケースを想定したり適切な方策を考えたりすることができますし、不要な揉め事を回避することもできます。
そして何より精神的・費用的な負担も軽減できますので、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。